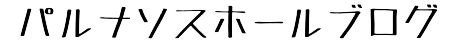
「姫路パルナソス音楽コンクール」は、将来性豊かな才能を持つアーティストを発掘し、姫路とゆかりを持ちながら今後の音楽活動支援を目的とするもので、受賞特典に副賞を授与するほか、次年度以降にオーケストラとの共演機会を提供しています。
今年は6月21日(土)に弦楽器部門、22日(日)にピアノ部門の本選があり、7名の皆さんが受賞されました。受賞者の皆さんをインタビューとともにご紹介します。


――演奏を終えて、今のお気持ちは。
独特の雰囲気に自分でも驚くほど緊張して弾き始めてしまいましたが、そんな自分を客観的に感じつつ、やっぱりこの曲が好きだなぁ、幸せだなぁと思いながら弾くことができた至福の時間でした。そんな実りある時間を過ごせたうえに、いい評価もいただき、本当に感謝しています。同時に、いただいた賞を励みに、もっとがんばらないと、と身の引き締まる思いです。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
舞台袖から出たとき、舞台の広さと高さに驚き、音を出すことに怖さを感じましたが、弾いていくうちに、響きの良さがとても心地よく、どんどん気持ちよく曲の世界に入り込んでいけました。
――どのような作品を勉強していますか。
今は、古典的なバッハ、モーツァルトやベートーヴェンから、ロマン派のパガニーニ、シューマン、ブラームス、サン=サーンス、ドヴォルザークやシベリウス、20世紀あたりに活躍したラフマニノフ、バルトークやショスタコーヴィチまで、いろんな時代や国の作曲家の作品に取り組んでいます。今後控えている本番に向けて、その時代背景や国のことなども学びながら、ソロ、弦楽四重奏、オーケストラとさまざまな編成で勉強しています。
――目標にしている演奏家はいますか。
好きなヴァイオリニストは、イツァーク・パールマンです。どんな曲でも技術的な難しさを感じさせず、音楽があふれ出ているところが大好きです。私もそんなふうに、音楽そのものを伝えられようになりたいです。そしてパールマンのように、世界中の人の心に音楽を届けたいです。
――受賞者演奏会への抱負や意気込みをお聞かせください。
素敵なパルナソスホールでの演奏機会をいただけてとても嬉しく、感謝しています。コンクールでは第1楽章を演奏したブラームスのコンチェルトの、第2、第3楽章を演奏します。自分なりに試行錯誤して、演奏会ではお客さまの心に響くようにがんばります!

《プロフィール》
相愛高校音楽科3年。第77回全日本学生音楽コンクール大阪大会第1位、全国大会第3位、サントリー芸術財団名器特別賞。第26回日本演奏家コンクール準グランプリ、弦楽器部門第1位。第30回神戸国際音楽コンクール最優秀賞、兵庫県知事賞等多数受賞。プロジェクトQ、小澤国際室内楽アカデミー受講。

――演奏を終えて、今のお気持ちは。
素晴らしい先生方に演奏を評価いただけたことはとても嬉しいですし、これからの練習の励みにもなります。練習を重ね、一度きりの本番を経験したことでの気づきもあり、また次の本番に向けてステップアップしていきたいです。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
とてもよく響くホールでした。本番までは緊張していましたが、舞台に出るとホールの洗練された空気に包み込まれるような感覚がありました。その空気が緊張を集中力へと変えてくれたように思います。おかげで曲ごとに気持ちを切り替えながら演奏できたと感じています。
――どのような作品を勉強していますか。
今は作曲家や時代、ジャンルなどに専門性を持たず、さまざまなクラシック曲に取り組んでいます。バッハなどの古い時代の曲や、チャイコフスキーやブラームスなどのロマン派、バルトークなどの民族音楽にも取り組み、それぞれの音楽の違いを学んでいます。
――目標にしている演奏家はいますか。また、将来どんな活動がしてみたいですか。
樫本大進さんやアウグスティン・ハーデリヒさん(Augustin Hadelich)、フランク・ペーター・ツィンマーマンさん(Frank Peter Zimmermann)です。将来は、これまで師事してきた先生方のように、音楽の素晴らしさを伝えていきたいです。
――受賞者演奏会への抱負や意気込みをお聞かせください。
大好きなホールで再び演奏させていただけることが今からとても楽しみです。少しでも多くの方に音楽、ヴァイオリンの魅力をお伝えできるよう精一杯がんばります。

《プロフィール》
第74回全日本学生音楽コンクール大阪大会高校の部第1位。第12回クオリア音楽コンクール コンサーティスト部門大賞。第8回豊中音楽コンクール弦楽器部門大学・一般の部第1位、豊中市長賞。2023、2024年度青山音楽財団奨学生。相愛大学音楽学部特別演奏家コース4年次に特別奨学生として在籍中。

――演奏を終えて、今のお気持ちは。
この3月に大学院を卒業後、今まで当たり前のようにあったレッスンがなくなり、そのような中で受けるコンクールは不安もありましたが、自己の成長のためにエントリーを決めました。演奏を評価していただき大変嬉しく、今後の励みになります。ありがとうございました。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
ホール全体によく響き、演奏しながら新しいインスピレーションが湧きました。また10月も演奏させていただけることを心から楽しみにしています。
――どのような作品を勉強していますか。
バロック時代から、古典時代、ロマン派時代、現代の作曲家の作品と、幅広く取り組んでいます。また近年はソロだけではなく、カルテットを中心とした室内楽にも特に力を入れて学んでおり、仲間と音楽を創り上げていく楽しさを実感しています。これからもソロ、室内楽の両方でさらにレパートリーを広げていきたいです。
――目標にしている演奏家はいますか。
新しい曲に取り組むたびに、いろんなCDやYouTubeを聴いて好きな演奏家に出会うので、書き切れないほどたくさんいますが、中でもハンガリーのチェリスト イシュトヴァーン・ヴァルダイやベルリンフィル奏者のブリュノ・ドルプレールは尊敬していて音源をたくさん聴きます。高校生の時初めて参加したアカデミーで講師として来日されたアンヌ・ガスティネルも大好きなチェリストです。ソロ・室内楽・オーケストラ、どのジャンルも大好きなので、マルチに活動できるチェリストになりたいです。
――受賞者演奏会への意気込みをお聞かせください。
さらに成長した姿をお見せできるように頑張ります。当日、会場でお会いできることを楽しみにしています。

《プロフィール》
8歳よりチェロを始める。第72回全日本学生音楽コンクール名古屋大会、全国大会第1位及び日本放送協会賞、かんぽ生命奨励賞。第15回ビバホールチェロコンクール第3位。相愛高校音楽科、相愛大学音楽学部を特別奨学生として卒業、東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程を修了。

――演奏を終えて、今のお気持ちは。
大好きなショパンのチェロソナタを弾くことができて、とても楽しかったです。スタッフの皆さまが温かく、緊張をほぐしてくださったおかげで、のびのび弾くことができました。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
池辺晋一郎先生が講評の際、本番で瞬時にホールの特性を把握してピアノとのバランスなどを考えなければいけないとおっしゃっていました。パルナソスホールはとても響きがいいホールで、自分の音がよく聞こえましたが、ピアノとのバランスという点ではまだまだ勉強しなくてはと先生のお言葉で思い、その点でもこのコンクールを受けてよかったと感じています。
――どのような作品を勉強していますか。
この春から大学に進学し、今はロマン派の曲を勉強しています。ベートーヴェンやショパンをじっくり勉強したいと思います。
――目標にしている演奏家はいますか。
憧れているのはスティーヴン・イッサーリスです。幅広い表現力を少しでも見習いたいと感じます。将来は留学をして、コンチェルトが弾けるソリストになりたいです。
――受賞者演奏会への意気込みをお聞かせください。
またパルナソスホールで演奏させていただけることが今から楽しみです。お客さまに楽しんでいただける演奏ができるよう、これからも日々練習を積んで参ります。

《プロフィール》
第26回姫路パルナソス音楽コンクール第3位。第77回全日本学生音楽コンクール大阪大会1位、全国大会1位、横浜市民賞、NHK会長賞。プロジェクトQにルシェリアクァルテットとして参加。小澤征爾音楽塾「椿姫」に首席チェロ奏者として参加。現在、桐朋学園大学音楽学部1年特待生。

表彰式にて
演奏するということは、いろんなものに似ています。たとえばスポーツ競技。山ほど練習を積んで、たった一回の本番に賭けなければならない。もし、そこでちょっとでもミスが出たら、それまでの練習が台無しになるかもしれないけれど、でも、そこでなにか大きなものを得ることができる。
演劇の舞台にも似ています。僕は音楽家ですけれども、半分は演劇人だといつも言っています。映画やドラマの音楽もたくさん書いてきましたが、特に演劇では五百数十本の音楽を書いていて、五百数十本の演劇のリハーサルもみてきています。セリフを言うとき、どの言葉に重きを置くか、どこを軽く言うか、どのくらいのテンポ、スピードでそれを言うか、どういう動きとともに言うかなどを役者は稽古してきて、そのとおりのことを本番でやる。しかも相手がいますから、一人で勝手なことはできない。そういうことにも似ていると思います。
ここはとても響きのいいホールですけれども、ステージでの練習はできなかったでしょうし、ピアノ伴奏者とのバランスというのも、事前に試してみるわけにはいかなかったと思います。伴奏が強すぎるとか、自分が強すぎるとか、そういうことを本番中に確かめながら、調整しながら演奏しなきゃならない。咄嗟の判断、咄嗟に調整する能力も問われるわけですよね。とてもたいへんなことだと思いますけど、それを体験することが、コンクールでいちばん大事なことなんです。
どういう結果を得るか、どういう成績を残すかが大事なんじゃなくて、たった一回きりの本番の場で、いろんな条件が重なる中で皆さんが体験したこと、それこそが、これからの演奏、これからの勉強に、必ず生きてくると思います。きょうの体験を、ぜひ財産にして、これからの皆さんの音楽に役立てていただきたいと思います。きょうの日を、忘れられない大切な一日として、心に留めておいてください。(談)