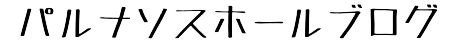
パルナソスホールで開催されている「音楽をのぞいてみよう!」は、現代の作曲家・池辺晋一郎さんが、作曲家ならではの視点でクラシック音楽を大解剖するコンサートシリーズです。バッハ、ベートーヴェン、チャイコフスキー…… と毎回一人の大作曲家に焦点を当て、名曲の数々を生演奏で楽しみながら、「こう書いたワケとは?」を読み解いていきます。
2021年9月に始まったこのシリーズが、12月に最終回を迎えます。企画の発案者であり各回の「お話」を担当する池辺さんに聞きました。

——シリーズのコンセプトと、10名の作曲家を選んだ理由をお聞かせください。
雑誌『音楽の友』に、作曲家一人につき2年、すなわち24回の連載をし、後日10冊の単行本(『音符たち』シリーズ)として上梓しました。10名の作曲家は①広範なジャンルに作品を書いている、②2年間の連載が可能なだけ、よく知られた作品の数がある、という条件で選びました。「音楽をのぞいてみよう!」は、それらを紙上でなく「音」として聴き、コメントをする、というコンセプトです。
ちなみに、このような理由にすると、ピアノ曲がほとんどのショパンやリスト、オペラがほとんどのヴェルディやワーグナー、「メサイア」のヘンデル、「展覧会の絵」のムソルグスキーなどは外れてしまう。それらは11冊目として『大作曲家の音符たち』にまとめました。
——これまで9回の公演がありました。
紙上から現実の音へ、というコンセプトは、やっている僕としても楽しく、有意義でした。実は連載中、また単行本化した際に、CD等、つまり「音」を付けてくれるとありがたい、という読者からの声が少なくありませんでしたが、「音符たち」というポリシーを崩したくなかった。それを一気に、コンサートの形で吐き出すことができたわけですから、自分の楽しさの理由もよくわかる、ということになります。
——特に印象に残っている回はありますか。
なんといっても2回目「シューベルト」で、新型コロナの渦中でした。姫路へ向かう前日だったか、僕は濃厚接触者になってしまいました。おかげさまで、おおごとにはならなかったのですが、コンサートはオンラインで実施することになってしまいました。現場スタッフの尽力で何とかやりおおせましたが、やはり隔靴掻痒のもどかしさがあったことは否定できません。ほかの仕事も含め、オンラインのコンサートはこれ一度だけです。とてもいい経験になりました。

写真:2022年1月30日開催 第2回シューベルト
他の回では、何度か連弾の片方としてピアノを弾くことになりましたが、これも実に楽しかったです。

写真:2022年12月3日開催 第4回ベートーヴェン

写真:2023年12月2日開催 第6回ドヴォルザーク
——次回はいよいよ最終回。オーストリアの作曲家・ハイドンです。
ハイドンは、やや地味な作曲家でしょう。しかし、さまざまなジャンルで「創始者」的な存在です。生涯のある時期まで典型的な「被雇用者」だったことが、社会の形こそ大きくちがう現代から、いわば先験的な立場として見つめることができる。作曲家は、アーティスト(芸術家)であると同時にアルティザン(職人)でもある。この視座で眺めてみると、ハイドンの大きさがさらによくわかります。
——もしも今後、続編あるいは新たな形で展開するなら?
ヴィヴァルディ、ショパン、リストなど、最初の項でお答えした「あるジャンルに特定される作曲家」を取り上げるチャンスにしたい。また、シベリウス、ボロディン、ムソルグスキーなど、近代に顕著になった民族主義的な傾向も。また、ヴェルディ、ワーグナー、ドニゼッティ、ビゼー、プッチーニなどで、オペラに特化する回もやってみたいですね。

©東京オペラシティ文化財団 撮影:武藤章
池辺晋一郎(作曲家)
1943年生まれ。交響曲、オペラ、映画・演劇・放送音楽など数多くの作品を手がけ、著書も多数。姫路市制100周年記念「交響詩ひめじ」、オペラ「千姫」を作曲。「交響詩ひめじ」合唱コンクール、「姫路パルナソス音楽コンクール」で第1回から審査員長を務めるなど姫路との縁は深く、2018年春に姫路市文化国際交流財団芸術監督に就任。平成30年度文化功労賞、令和4年度旭日中綬章。