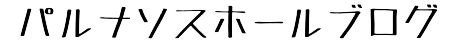
「姫路パルナソス音楽コンクール」は、将来性豊かな才能を持つアーティストを発掘し、姫路とゆかりを持ちながら今後の音楽活動支援を目的とするもので、受賞特典に副賞を授与するほか、次年度以降にオーケストラとの共演機会を提供しています。
今年は6月21日(土)に弦楽器部門、22日(日)にピアノ部門の本選がありました。受賞者の皆さんをインタビューとともにご紹介します。


――演奏を終えて、今のお気持ちは。
今回初めてこのコンクールに参加させていただきました。このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。コンクールスタッフの皆さんや審査員の方々に、改めて御礼申し上げます。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
繊細にメンテナンスされている音の立ち上がりの良いピアノと、残響の豊かな会場に身を委ねながら、自分がその瞬間に描きたい音楽を可能にする、私にとっては理想的な会場であったと思います。
ホール背面に立派なオルガンがあることから、きっと良い音響空間なのではないかと演奏前から予測していました。
――どのような作品を勉強していますか。
常にあらゆる時代の作曲家の作品に取り組むことを心掛けています。学部時代にオルガンを専門的に学んでいたこともあり、ルネサンスやバロック時代のさまざまな組曲を含む教会音楽や、複数の旋律が折り重なる対位法的な器楽作品、また、ブラームス、シューマン、リストと彼の弟子のロイプケといったドイツ・ロマン派黄金期のピアノ・オルガンの作品や、著書『わが音楽語法』で有名なメシアンなど、ロマン派以降の繊細さや劇的な響きを併せ持つ作品にも関心を持ち、これまでさまざまな作品に取り組んできました。
最近はショパン、シューマン、リストなどのロマン派のソロ作品を中心に、室内楽や歌曲の伴奏などにも積極的に取り組んでいます。
――目標にしている演奏家はいますか。
今は亡き音楽家ですが、個人的にはアレクセイ・スルタノフ(1969-2005)氏を敬愛しています。残念ながら音源や映像でしか観たことはありませんが、楽器のポテンシャルを最大限に引き出し聴衆を一気に熱狂させる力、その類い稀なカリスマ性に惹かれました。もちろん、若さによる可能性を秘めた演奏と、巨匠の熟成した演奏を比較してしまうと、両者の解釈の方向性はまったく異なるのですが、そのような相反するスタイルを汲み取った上で、唯一無二の創造性を高めていきたいと考えています。
――将来、どんな活動がしてみたいですか。
以前から思っていたことですが、私は、ピアノをはじめとする鍵盤楽器それ自体に心を揺さぶられたことはありませんでした。あくまで楽器は媒体であり、演奏するにあたって、西洋楽器であれば何でも良かったのです。たまたま辿り着いたピアノという楽器を用いて、または先に述べたようにオルガンを学んでいることを強みに、今後はピアノとオルガン作品の音楽を同時に愉しめる演奏会を実現できればと思っています。
――受賞者演奏会への抱負や意気込みをお聞かせください。
またこの素晴らしいホールで演奏できることを大変嬉しく思います。私事ですが、9月からスイスへ留学するため、一時帰国して演奏することになります。10月には、ロマン派の名作を演奏しようと考えています。皆さまに足をお運びいただければ幸いです。

《プロフィール》
昭和音楽大学修士課程に特待生として在学中。スコラ・カントルム音楽院にて審査員満場一致の成績でディプロマを取得。第12回国際ピアノコンクール Città di San Donà di Piave 第2位。第32回宝塚ベガ音楽コンクール第1位、兵庫県知事賞。第46回ピティナ・ピアノコンペティションPre特級銀賞。

――演奏を終えて、今のお気持ちは。
姫路パルナソス音楽コンクールに参加させていただくのは初めてで、今回、舞台に乗せるのが初めての作品もあり不安もありましたが、今は無事に演奏できてホッとしています。本選の舞台では緊張や不安はもちろんありましたが、それぞれの作品の良さを伝えたい、自分自身の音楽を表現しようと思い、演奏しました。コンクールの舞台ではありましたが、自分の音や響きをよく聴き、会場の皆さまと音楽を共有することに努めました。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
高校の敷地内にあるとは思えないような趣きのある素敵なホールで、響きも素晴らしかったです。また演奏できる機会をいただけて、大変光栄です。
――どのような作品を勉強していますか。
クラシック音楽を中心に勉強しています。大学では、バロック音楽から近現代の作品まで、幅広い時代の作品に取り組んでいます。なかでも、ロマン派のショパンやメンデルスゾーンの歌心のある作品や、近現代のラフマニノフやプロコフィエフのサルカズムを感じさせる音楽に興味を持って勉強しています。
――目標にしている演奏家はいますか。
シャルル・リシャール=アムランの演奏をリサイタルで初めて聴いたとき、その音色の多彩さ、美しさに衝撃を覚えました。私も、音色の美しさで人を魅了できるピアニストになりたいと思います。
――将来はどんな活動がしてみたいですか。
作曲家の意図をきちんと汲み取り、それを伝えられるピアニストになりたいです。そして「この人のピアノをまた聴きたい」と思っていただけるような演奏をしたいです。リサイタル活動をはじめ、オーケストラとの共演や、室内楽など、いろいろな音楽経験をしていきたいです。
――受賞者演奏会への抱負や意気込みをお聞かせください。
もう一度パルナソスホールで演奏できる機会をいただき、とても光栄に思っています。大好きな作品の良さを皆さまに伝えられるように、日々精進したいと思っております。

《プロフィール》
京都市立芸術大学に在学中。日本クラシック音楽コンクールピアノ部門大学生の部第2位。入賞者演奏会でオーケストラと共演。堺市新人音楽コンクール最優秀賞。日本国際音楽コンペティション大学生部門第1位。ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 全国大会金賞、アジア大会銀賞。ウィーン国立音楽大学にてディプロマを取得。

――演奏を終えて、今のお気持ちは。
とても緊張していましたが、作品をもっと好きになることができた瞬間があり、賞をいただけて嬉しいです。でも、もっとこうできていればと悔しさもあります。
――パルナソスホールで演奏してみて、いかがでしたか。
内装も綺麗で、響きも素晴らしかったです。大きくて、残響があるホールなので、聴いてくださる方との距離に壁ができないよう、音を遠くに飛ばすように、届けるように、意識して弾きました。
――どのような作品を勉強していますか。
バッハなどのバロック時代から現代まで、幅広く勉強しています。今回のコンクールではドイツ、ロシア、スペインの作曲家を並べたように、さまざまな国の音楽も勉強しています。
――目標にしている演奏家はいますか。また、将来どんな活動がしてみたいですか。
好きなピアニストは、アレクサンドル・カントロフとマルタ・アルゲリッチです。強い意志と情熱、音の質で聴衆を虜にできるようなピアニストになりたいです。将来は、演奏家としてはもちろん、身体の使い方の研究や、自分の経験からさまざまなアプローチができる指導者になりたいです。
――受賞者演奏会への抱負や意気込みなどを教えてください。
再びパルナソスホールで演奏できることが決まり、今からとても楽しみです。自分を存分に表現できる作品を選びたいと思います!

《プロフィール》
第73回全日本学生音楽コンクール高校生の部 東京大会第1位、全国大会第2位。第41回かながわ音楽コンクールピアノ部門一般の部第1位。東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。在学中に短期留学奨学生として英国ギルドホール音楽演劇学校に留学。

表彰式にて
僕が若い頃、僕よりさらに若いピアニストと話していて、そのピアニストが「ラヴェルのコンチェルトを弾くと海がみえるんだ」って言ったんです。それを僕がなにかの席で話しましたら、そこに音楽界の大御所である大先生がいらっしゃって、「なにが海だ、あの曲と海はなんの関係もない、そんな話を『素敵だな』って話すとは」と怒られました。
19世紀にハンスリックという音楽学者がいました。彼は「音楽は、あらゆるものと関係がない。音楽は音の組み立てによる芸術であって、なにかを描写したりなにかを表現したりはしない」と言っています。一方で、チャイコフスキーは「すべての音楽はなにかを表現している。厳密に言えば、すべての音楽は描写音楽である」と言っています。
音楽が、音による組み立てであることは間違いない。それを承知したうえで、その次の段階として、なにを表現するのか、それがやはり、演奏するという行為においてはとても大切なことだと思います。ただ楽譜どおりに弾けばいいのなら、AIが機械的に演奏すればそれでいいことになってしまう。この音楽でなにをどう表したいのか、自分なりの考えや思い、主張を込めてこそ演奏になるんです。
なぜ人間が、演奏という行為を通して音楽を味わうのか、なぜ演奏を聴いて楽しんだり、なにかを感じたりするかというと、そこに音楽以外のなにかが加わるからですよね。そういうことも考えて演奏していくと、自分なりの音楽というものがだんだんできあがっていくと思います。楽譜どおりにただ弾けばいいのではないということを、本質的に理解していただきたい。
ここで演奏したことは、必ずこれからの活動の財産になります。きょうの体験こそを大事に、これからの音楽に生かすように心がけていただきたいし、そのためにコンクールを受けたんだと思ってほしい。結果よりももっと大事なことがあるということを、忘れないでください。(談)